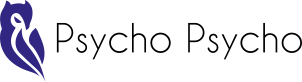精神障害は様々な症状を呈するものが多く、適切な鑑別診断を行うことがより良い治療を行ううえで欠かせません。
今回は精神障害の分類を示した米国精神医学会による精神障害の診断と統計マニュアルであるDSMを取り上げます。DSM日本語版とはいったいどのようなものなのでしょうか。その歴史や使い方、ICDとの違いなどについてご紹介します。
目次
DSM日本語版とは
DSMとは、米国精神医学会が編集している精神疾患の診断・統計マニュアルのことであり、Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの頭文字をとり、DSMと呼ばれています。
DSMの歴史
DSMの開発は1950年代にまで遡り、現代に至るまで複数回の改訂がなされています。
病因論とDSMの開発まで
DSMの開発まで、精神疾患を取り扱う精神医学の領域では、フロイトから始まった精神分析の理論が主流であり、精神疾患の鑑別診断も行われていました。
このような方法で中核となっているのは病因論と呼ばれる考えです。
病因論とは、精神疾患の原因により疾病を分類する手法のことで、次のような種類があります。
【病因論】
- 外因性:脳の損傷や臓器の異常など身体の器質的な異常により精神症状を呈するもの
- 心因性:ストレスや内的な葛藤など心理的な要因により精神症状を呈するもの
- 内因性:(いずれ原因が特定されるかもしれないが)現代の医学では原因が不明であり、外因性・心因性ともいえない精神疾患
そして、DSMの初版が1952年に発行され、1968年にその初めての改訂がなされたDSM-Ⅱまでは病因論に基づく診断が行われていました。
そして、その病因論による診断がなされているなかでのDSMの位置付けは、診断基準としてではなく、あくまで精神障害の分類を示した図鑑のようなものだったのです。
しかし、DSM-Ⅲの登場により、大きな転機を迎えます。
DSM-Ⅲの登場
DSM-Ⅱへと改訂がなされた1970年代では、精神科での鑑別診断の精度の低さが批判されるようになってきていました。
その背景には、統一された診断の基準がないことにより、精神疾患を特定するための情報収集の方法がバラバラで、それぞれの精神科医の裁量に任されていたことによると言われています。
そのため、どのような精神科医を訪れたとしても同じ患者であれば、同じ診断が下されるようなマニュアルとなる診断基準が求められるようになったのです。
こうして1980年には明確な診断マニュアルとなりうるDSM-Ⅲが発行されます。
DSM-Ⅲの特徴は次の3つです。
【DSM-Ⅲの特徴】
- 障害という記載
- 操作的診断基準の採用
- 多軸評価システムの採用
精神「疾患」や「疾病」というよう度には健康という状態の対極に存在する病である、つまり生きていく上で不都合な状態を意味しています。
これは、差別や偏見を助長する一端を担っており、精神障害が持つ本来の姿から離れ独り歩きし、2次障害を招くなど深刻な事態を招きかねません。
そのため、疾病(Disiese)から障害(Disorder)へと名称を変更することで、患者自身の2次予防(重篤化を防ぐ)や3次予防(再発を防ぐ)に繋げようとしていたのでしょう。
また、操作的診断基準と呼ばれる、外から観察可能な症状がいくつ当てはまるかというチェックリストに基づき診断を試みようとしたことは病因論を脱却し症候論を採用することで、誰であっても同じ患者には同じ診断が下せるようその信頼性を高める働きがあるものでした。
DSM-Ⅳ及びDSM-5への改訂
その後、DSM-Ⅳへの改訂においては基本的にDSM-Ⅲのシステムを踏襲する形となりました。
診断分類においてはDSM-Ⅲの265種から374種へと細分化なされ、それに伴い診断の重複も問題視されていたため、分類の見直しがなされました。
しかし、DSMが広く使用されるようになると、いずれのカテゴリにおいても合併症が多くみられ、実際の心理臨床の現場では、どの疾患に分類すればよいのかが曖昧になっているという問題がありました。
このような特定のカテゴリに当てはめる診断方式は特定不能の障害という診断を引き起こしやすく、治療方針を決定するうえで問題となります。
このような背景からDSM-5では、多軸評価システムを廃止し、ディメンショナルモデルとスペクトラム概念を導入しました。
このような制度は、何らかの疾患概念を症状の有無や重篤度の基準によって分類するのではなく、それぞれの患者が抱える症状の背景にある障害は明瞭な境界線を持たない連続体(スペクトラム)であるというものです。
ディメンション診断では、各症状の重症度を「症状なし」から「重度」まで評価を行います。
これにより、様々な臨床的特徴を次元とみなし病態を系統的に捉えることができるようになったのです。
ICDとの違い
DSMに加え、心理臨床の現場において重宝される診断基準にICDと呼ばれるものがあります。
これは、世界保健機関(WHO)が発行している国際疾病分類(International Classification of Diseases)の略称です。
ICDは1900年に初版が発行されてから現在に至るまで、9回の改訂がなされており、最新版はICD-10になります。
ICDも精神障害に関する分類と診断の基準を明記しているものではありますが、DSMとは次のような違いがあります。
【DSMとICDの違い】
- 対象の疾患:DSMと異なり、ICDは精神疾患だけでなく、病気やケガなども含まれる
- 使用目的:DSMは主に医師が診断を下すために用いられるが、ICDは国際的な疾病の調査や行政機関などで用いられる
- 費用:DSMは有料だが、ICDは無料で使用できる
DSM-5による精神障害の分類
DSMにおける精神障害の分類は、大カテゴリと小カテゴリに分けられます。
そして、DSM-5においては、それぞれの大カテゴリは22個に分けられます。
小カテゴリを含めすべてをご紹介すると煩雑になってしまうため、今回は大カテゴリの種類をご紹介します。
【DSM-5の分類】
- 神経発達症群/神経発達障害群(知的障害や発達障害など)
- 統合失調スペクトラム障害および他の精神病性障害群(統合失調症や統合失調型パーソナリティ障害など)
- 双極性障害および関連障害群(双極性障害や気分循環性障害など)
- 抑うつ障害群(うつ病や気分変調症など)
- 不安症群/不安障害群(恐怖症やパニック障害など)
- 強迫症および関連症群/強迫性障害および関連障害群
- 心的外傷およびストレス因関連障害群(PTSDや適応障害など)
- 解離症群/解離性障害群(解離性同一障害や解離性健忘など)
- 身体症状症および関連症群(病気不安症や転換性障害など)
- 食行動障害および摂食障害群(拒食症や過食症など)
- 排泄症群(遺尿症や遺糞症など)
- 睡眠-覚醒障害群(不眠症やナルコレプシーなど)
- 性機能不全群(EDや性欲低下障害など)
- 性別違和(LGBTに関わる、いわゆる性同一性障害)
- 秩序破壊的・衝動制御。素行症群(反抗挑戦性障害や放火症など)
- 物質関連障害および嗜癖性障害群(アルコール依存症や薬物依存など)
- 神経認知障害群(せん妄や認知症など)
- パーソナリティ障害群
- パラフィリア障害群(露出障害や小児性愛障害など)
- その他の精神疾患群
- 医薬品誘発性運動症群およびその他の医薬品有害作用
- 臨床的関与の対象となることのある他の状態
このような、大カテゴリの中には様々な障害が含まれていますが、例えば「統合失調スペクトラム障害および他の精神病性障害群」では、統合失調型パーソナリティ障害から妄想性障害、短期精神病性障害、統合失調症様障害、統合失調症など様々な障害が含まれます。
DSM-5ではスペクトラムの考えを導入していることを先にご紹介しましたが、このような障害は治療経過によって、他の障害へと移り変わることも多いという特徴があります(例えば、統合失調型パーソナリティ障害から統合失調症へと移行するなど)。
そのため、現時点で現れている症状から診断を行うと共に、これから移行する可能性のある障害も含めて判断を行うことができるようになったと言えるでしょう。
DSMの使い方
操作的診断基準とは、どのような症状が、どのくらいの種類同時に現れ、どのくらい持続しているかという明確な基準を設け、その基準を超えていれば、精神障害であると判断するという方法のことです。
これはそれまで主流であった病因論からの脱却を目指しているものであると言えます。
もちろん、現代の精神医学でも病因論が全く考慮されないわけではありませんが、DSMではこの操作的診断基準により、外側に現れた、観察可能な症状を把握することによってどのような障害なのかを判断する症候論の立場を採用しています。
多軸評価システムは、次の5つの軸から多面的に精神障害を捉えるという方法です。
【多軸評価システムの軸】
- 臨床疾患
- 人格障害・精神遅滞
- 一般身体疾患
- 心理社会的及び環境問題
- 機能全般的評価
このような多面的な視点から精神障害を診断しようとする試みは、精神・身体症状だけではなく、患者が直面している社会活動への参加の制約など、精神障害を抱えている人の不適応の困難さをより適切に捉えることを促します。
しかし、DSM-5への改訂によりディメンション診断が取り入れられたことにより、各障害はスペクトラムであるという前提から、それぞれの障害の重症度を%表示で示し、現在の病像がどのような状態であるかを捉えることで診断が行われます。
DSMを学ぶための本
DSMを学ぶための本についてまとめました。
DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引
DSMの最新版であるDSM-5の診断手引きです。
DSM-5には膨大な記載があり、手に取るだけでもめまいがしそうなページ数がありますが、その中から診断基準のみを抜粋しているため、後述のトレーニングブックと合わせて用いることで効率的に勉強できるはずです。
DSM-5 診断トレーニングブック: 診断基準を使いこなすための演習問題500
DSM-5に基づいた診断を行うためには、事例から特徴的な症状を的確に拾っていく視点が求められます。
豊富な障害の事例からどのような診断であるかを演習する事例集である本書を用いてDSMによる診断の目を養いましょう。
DSMによる診断は完全か?
DSMの登場により、心理臨床の現場における診断の信頼性を高めることができたということは精神医療の領域において非常に大きな進歩でしょう。
しかし、精神障害については未だ未解明な部分も多く、伝統的な医学的診断の手法も侮ることはできません。
また、DSMの横断列挙的な診断名の記載は初学者に精神疾患の全体像をとらえるうえで混乱を招きやすいという批判もあります。
ぜひ様々な視点から精神障害を学び、的確にとらえる目を養いましょう。
【参考文献】
- 田巻義孝・堀田千絵・加藤美朗(2015)『精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)の改訂について』関西福祉科学大学紀要(19), 37-58
- 石坂好樹(2016)『DSM-5拾い読み:—子どもの精神障害を中心として—』児童青年精神医学とその近接領域 57(1), 205-218
- 美馬達哉(2018)『DSM的理性とその不満』保健医療社会学論集 28(2), 54-64
- 日本精神神経学会精神科病名検討連絡会(2014)『DSM‒5 病名・用語翻訳ガイドライン(初版)』精神神経学雑誌116-6, 429‒457