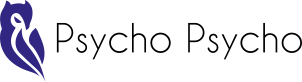言葉にはコミュニケーションを行うという機能に加え、思考の道具として用いられる役割を持っています。これは心理学的には内言と外言という用語で表されます。
しかし、生まれながらにして言葉を話せるわけではない幼児が発達の過程においてどのように思考の道具として言葉を用いていくようになるのでしょうか。今回は内言・外言の読み方から、その意味や役割について解説していきます。
目次
内言・外言とは
内言・外言とはどのようなものなのでしょうか。
内言・外言の読み方と意味
内言は「ないげん」、外言は「がいげん」と読みます。
そして、それぞれは次のような意味を持っています。
- 内言:自分への語りかけや、声に出すことなく、思考のための道具として自分自身の頭の中で用いられる言葉のこと。思考の道具であるため、文法に則った形をとるとは限らず、述語が中心の構造となる。
- 外言:他者に向かって音声として発せられる言葉のこと。主語が主体の構造を持ち、文法的に正しい形を持っているという特徴がある。
幼児期の発達と内言・外言:幼児の独り言を巡る論争
幼児期の発達に伴う内言・外言の捉え方については大きく分けて2つの主張がなされてきました。
それは、幼児期に特徴的な自己中心語において、内言と外言はどのように関わっているのかという議論です。
ピアジェの主張
認知発達論を唱えたことで有名なピアジェ,J.は自己中心語つまり、幼児のいう独り言は前操作期と呼ばれる時期に特徴的にみられる自己中心性に基づいていると考えました。
自己中心性とは、認知機能が十分に発達していないことによって、他者の視点から物事を捉えることが出来ない状態を言います。
そして、次の具体的操作期の段階へ移行するにつれ、脱中心化が起こり、非社会的な独り言自体は消失していくのだと主張しました。
そのためピアジェは、認知機能が十分に発達し、思考ができるようになってから他者へのコミュニケーションを目的とした会話ができるようになる、つまり思考の道具である内言が出来てから外言ができるという発達を主張したのです。
ヴィゴツキーの主張
これに異を唱えたのがヴィゴツキー,L.S.です。ヴィゴツキーはピアジェとは真逆の外言から内言という発達的な経路を想定しました。
ヴィゴツキーは、幼児がまず他者とコミュニケーションをとるために他者へとむけられた外言を獲得するとしています。そして、そこから自己へ向けられた思考の道具としての内言が分化していくと主張しました。
ただ、幼児においては外言と内言が未分化な状態です。
そのため、思考の道具として本来は発話しないはずである内言に音声が伴ってしまうため、他者から見ると独り言をつぶやいているように見えると考えました。
なお、内言と外言の分化が完全になされることにより、幼児の独り言は消失します。
この論争は最終的にヴィゴツキーの主張が主流な考えとして浸透しています。
内言・外言を扱った心理学理論
内言や外言が人間の思考や行動にどのようなかかわりを持っているのかについて注目した研究をご紹介します。
ルリヤの発達モデル
ルリヤ,A.R.は、言葉が行動の調節へ影響を与える過程をモデル化したことで有名な研究者です。
ルリヤは具体的に次のような実験を幼児に対し行いました。
【go/no-go課題】
この課題はランプが2つとバルブを用いて行われます。
具体的には、赤いランプが点灯したときはバルブを押させ、緑のランプが点灯した際にはバルブを押さないよう被検者に教示します。
この手続きに言語での命令を混ぜると、どのような結果になるのかをルリヤは検討しました。
結果としては、2歳頃の幼児に対し、「赤いランプがついたらバルブを押しなさい」という教示に対し、ランプの点等の有無に関わらずバルブを押し続けました。そして、この反応に対し「押してはダメ」と止めようとすると、かえって押す反応が強まってしまったのです。
そして、年齢が高くなるにつれ、言語による命令を交えて徐々に行動の調整ができるようになる様子が観察されました。
ルリヤの言語による運動調整機能の発達段階
ルリヤは『go/no-go課題』を通じて、次のような段階を経て、言語が運動を調整する機能が発達すると結論付けました。
- 他者からの言語教示に反応する段階
- 自分への外言によって行動を調整できる段階
- 自分への内言によって行動を調整できる段階
これらはつまり何を意味しているのでしょうか。
第1段階
第1段階は、外からの言語的刺激が、幼児のバルブを押す行動を促進したという意味で、運動を始めさせる刺激としての意味を持っています。
これは他者から与えられる言語教示であり、それ以降の段階では次第にその教示が内化されていきます。
第2段階
第2段階では、赤いランプが点灯したら自分で「押せ」という言葉を唱えるよう教示すると、バルブを押せるようになる段階です。この年齢の段階はおよそ3~4歳ほどと言われています。
つまり、他者が言わなければバルブを押さなかった幼児が、自分で音声による命令を出すことによって行動を始めることが出来る段階です。
これは、他者から与えられる外からの音声刺激が内化され、自分から発する音声でも他者からの教示と同様の効果を持っている状態ということが出来ます。
※ただし、この効果がみられるのは運動の始動に関してのみであり、活動をストップさせるよう自分で声に出しても行動をやめることが難しいとされています。
第3段階
第3段階は、自分で声を出すことがなくても行動を始発・停止できる状態です。この状態が内言を獲得した状態であり、5~6歳頃から可能となり、7~8歳で完成するとされています。
このように行動の調整と言語の関わりは、①外界からの言語的刺激②自分への外言③内言という発達のプロセスを経ていくのです。
内言・外言について学べる本
内言・外言について学べる本をまとめました。
社会と文化の心理学ーヴィゴツキーに学ぶ
内言と外言という用語を学ぶ上でヴィゴツキーの知見を避けて通ることはできません。
ヴィゴツキーは内言・外言以外にも発達の最近接領域といった発達心理学において現在でも重視されている発見をした研究者です。
そんなヴィゴツキーの研究から得られた知見を網羅的にまとめてある本書を手に取り、内言・外言への学びを深めましょう。
新装版 人間の脳と心理過程
ルリヤは神経心理学者もしくは神経言語学者などと呼ばれるように、脳と心の関係についての研究に情熱を注いだ研究者です。
上記でも紹介したgo/no-go課題を行った研究者としても有名なため、一度目を通しておくと、外言から内言へと変わっていくことで外から見える行動がどのように変化していくかについて理解が深まるでしょう。
私たちに身近な内言と外言
人とのコミュニケーションの手段としての外言だけではなく、内言も何か考え事をするときに用いられる非常に身近な言葉です。
しかし、子どもは発達とともに内言を身に着けていくため、子どもと接するときにはその子の年齢や認知発達だけでなく、外言・内言の獲得の度合いに注目することも良いかもしれません。
【参考文献】
- 土屋宣明(2007)『抑制機能の分類に関する研究』立命館文學 (599), 100-109
- 前田明日香(2007)『行動調整機能における研究動向とその課題--Luriaの脳機能モデルへの発達論的アプローチの可能性』立命館産業社会論集 43(3), 79-98
- 阿部千春(1966)『言語調整機能の発達的検討』教育心理学研究 14(3), 139-146,189